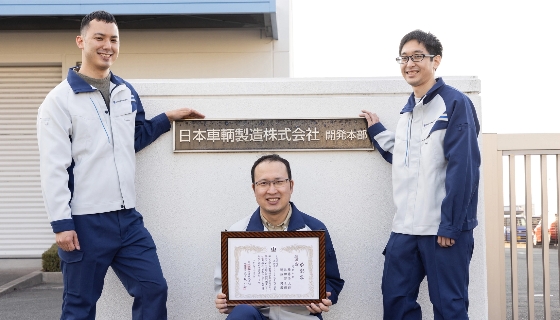未来をつくる
ゆっくり、安全に、時間内に、確実に運ぶ。
「H3ロケット」の運搬に求められる高度な要望を
日本車両の技術力とチーム力で応えました。
PROJECT MEMBER

輸機・インフラ本部
製造部 製造一課(製造)
2010年入社
※現 管理部所属

輸機・インフラ本部
技術部 技術第二グループ(設計)
2013年入社
※現 製造部所属

輸機・インフラ本部
技術部 技術第四グループ(設計)
2013年入社
※所属・組織名は取材当時のものです
H3ロケットは、JAXAが種子島宇宙センターから
打ち上げを予定している次世代の大型ロケットです。
産業基盤の維持を目的とした大型プロジェクトにおいて、
日本車両は、ロケットを発射台ごと組立棟から射点まで運搬する「ML運搬台車」の開発・製造に関わりました。
これまでにないスケール感あるプロジェクトでは、
設計、制御、製造、試験、保守・・・のあらゆる部門で
大きく立ちはだかる壁を、チーム一丸となって乗り越えてきました。
H3開発プロジェクトでは、
運搬台車の更新も求められていました。

日本の新しい基幹ロケットH3ロケットは、現在運用中のH-ⅡAロケットの後継機として開発プロジェクトが立ち上がりました。ロケット開発は、ロケット本体の開発にとどまらず、新しいロケットに対応した周辺設備の開発も同時に行われます。その中の1つがロケット組立棟から射点まで発射台に載せたロケットを運ぶ運搬台車です。既存設備は、約20年運用されていて老朽化が進んでいました。また、性能・耐久面でそのままH3ロケットの運搬に使用できないため、新たな運搬台車の開発が必須でした。そこで日本車両が「ML運搬台車」の開発・製造に関わることになりました。
プロジェクトがスタートしたのは2015年。ML運搬台車とは、移動発射台(ML)上で組立・整備されたロケットをMLごと持ち上げ、大型ロケット組立棟から射点まで運搬する車両です。新しいML運搬台車に求められるさまざまな要件に応えるべく、日本車両の技術者たちが高い技術力とチームワーク、そして高みを目指して妥協を許さない姿勢で開発に取り組み、日本の商業衛星打ち上げ事業に貢献しています。
強く、軽く。
日本車両の技術を詰め込んだフレーム設計。

設計でクリアすべき課題となったのは「重量」です。H3ロケットは、これまでのロケットよりも重量が増え、ロケットとMLを合わせた積載量は、最大約1460トン。さらにH3ロケットでは、これまでの打ち上げ回数を上回る年間6機程度を安定して打ち上げるという計画を掲げています。また種子島の強風にも耐えるべく、フレーム設計では、重量を支えるための強度と、使用頻度の高まりに対応する耐久性が求められました。フレームは強度を司る重要部分です。過去、日本車両のあらゆる案件を振り返っても、これほど重量のある積載物を運んだ事例がありません。そこで設計では、素材から形状まであらゆる可能性を検討し、最終的には橋梁等で用いられるトラス構造をフレーム設計に採用し、強度を確保しました。別事業の技術を横展開することでより良い解決策が導かれたのは、日本車両ならではの強みです。
次の課題は「軽さ」でした。強度だけに着目して素材を構成すると、車両の重量が重くなります。走路の制約から運搬台車の重量に制限があり「強くしながら軽くする」という設計には幾度かの壁がありました。素材構成を検討しつつ、フレーム設計では重量がかかる箇所とそうでない箇所を正確に導き出し、荷重に合わせた設計を行いました。
水平精度0.2°以内。
制御設計では、超微細な要求をクリアしました。

H3ロケットを安全に確実に運搬するために、開発では高度な要求値をクリアしなければなりません。自動運転によって安全に運搬するために「水平精度は0.2°以内」「加減速度は0.08G以内」と定められていました。水平制御の制御設計では、事前にある程度、目処がついた設計方法がありました。しかし、その方法でシミュレーションしたところ、想像以上に複雑で水平維持制御が動かず、再検討を余儀なくされました。条件は「水平を維持すること」「高さを一定に保つこと」。これらを両立させることが求められます。そこで、従来は車体中央の高さの値を測っていたところを、地面から最も近い場所の高さを測定することにしました。新しい方法でシミュレーションし、お客様にも高く評価をいただきました。
設計にはあらゆる方法があります。その中から最適な解を見つけるために、幾度となく解析を行うのですが、設計段階では、実機はもちろん、試作機などの実物がありません。解析数値では合格ラインを得たとしても、「本当に大丈夫なのか」「もっと良くならないか」とその先のもう一歩まで踏み込み、納得するまで解析を続ける姿勢が日本車両の品質を支えています。
環境条件を合わせた試験走行のために、
種子島宇宙センターの環境を社内敷地内にて再現。

製造では、組付と試験に困難を極めました。基本的な製造は豊川製作所で行われました*が、豊川製作所には走行試験を行うスペースがなく、代わりに衣浦製作所で試験を行うことにしました。そのため、豊川製作所で輸送できる限界まで組み付け、さらに衣浦製作所で仕上げをするという2段階作業となりました。衣浦製作所では屋外作業だったため、天候の変化や台風などによるリスクが工程を阻んでいます。そんな中、頼りになったのは現場の作業員たちです。ボルトの締め付け1本にも妥協を許さない意識の高さが変化の多い作業工程の中でも、品質を守り抜きました。
走行試験は、本プロジェクトの最大課題といって過言ではありません。まずは現地の再現です。種子島宇宙センターと同じ環境を再現すべく、衣浦製作所のヤードを整地した上に、鉄板を敷き、平らなスペースを作りました。ML運搬台車は磁気センサーによる倣い制御で走行するため、鉄板の上に磁石を配置しました。車両側では、MLを模した門型の治具を製作し、そこに鉄板を積み、H3ロケットを積載した状態を作り出しました。ML運搬台車では「異常発生時は速やかに復旧する」という要件があったため、試験には通常試験のほか、異常時の動作・復旧確認も盛り込みました。
これらの作業には、豊川製作所から衣浦製作所までの運搬も課題でした。非常に大きな製品であり、車体を結合してからも各部品を組み付けていったため、輸送状態での重量を一括して事前に測定することができません。そのため、輸送の積載制限重量以下になるよう部品を取り外し、到着後、再び組み付ける必要がありました。しかも部品は3700種類、8万個以上。主要部品に限定してカタログ値、実測値、設計値を用いて輸送状態の重量を測定しました。輸送時に想定と異なる場合もあり、その場での対応にも現場力が求められました。
*2020年まで、輸送機器部門は豊川製作所にありました。現在は衣浦製作所に移転しています。
全員が抱いていた「いいものを作りたい」という思い。
得た経験と技術を今後のものづくりに展開します。


こうして種子島宇宙センターに到着したML運搬台車は、2021年3月、H3ロケット試験機1号機の機体移動試験にて求められる性能を発揮しました。設計、制御、製造、品質保証など関わった全部署の社員が、現地にて車両が動く姿を目にし、大きな感動が広がりました。月並みですが、ものづくりにおいて「現地でモノが動く」ということほど嬉しいことはありません。
種子島宇宙センターでの最後の組み立てや試験でも計画とおりに遂行でき、お客様からは「日車さんはいつも工程通りですね」とお褒めの言葉をいただきました。これもすべて関わるすべてのスタッフが「最高品質のものづくり」という同じ目標に向かって進めたからこそ。幾度となく検証を重ねたり、お客様の意見を反映することに尽くしたり、現場からの声を改善につなげたり…、度重なる苦難に全員が考え、行動してきたことが成果となりました。
現在は、これらの経験やノウハウが新しいAGV開発の検討に用いられるなど、社内での活用が進んでいます。
技術の横展開や転用を視野に入れ、今後の日本車両の技術を発展させて社会基盤の構築に寄与して参ります。